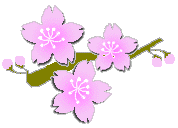���Ă̕]��
�W���C�X�E�b�E���u���i�A�����J�A�R�����h��w���j�w�������j�̌��t
���{�̔s��A����͂������A�W�A�S��̓Ɨ��^���ɂ͌���I�ȈӖ��������Ă����B
���܂�^�̓Ɨ����m�łƂ����\���ƂȂ�Ɠ����ɁA���m�̐A���n�x�z�̕������A�����Ă͂Ȃ�Ȃ�������̉\���Ƃ��ĕ����яオ���Ă����̂ł���B
������`�҂́A���{��̊��Ԓ��Ɂi���{�R�ɂ��j�g�ɂ������M�A�R���P���A�����\�͂������āA���m�̐A���n�x�z���A�ɑR�����B
�����āA���{�ɂ���̉��ŁA������`�A�Ɨ��v���͂��͂�����Ԃ��Ȃ��Ƃ���܂Ői��ł��܂����Ƃ������Ƃ��C�M���X�A�I�����_�͐��ɂȂ��Ďv���m�邱�ƂɂȂ�̂ł���B�i�����j
����ɁA���{�͓Ɨ��^����͂Â��A������`�ɕ��͂�^�����B
���{�R�s���̐Ղɂ́A��x�ƊO���x�z�͋����܂��Ƃ������M�ƁA���̎��M�𗠕t�����i�Ƃ��c�����̂ł���B
����A�W�A�̐l�Ԃ͂��܂═�����ɂ��A�P����ς�ł���A�����́A�g�D�͂�g�ɂ��A�Ɨ������߂�S�ł���ӎu�Ɏx�����Ă����B
�i�u����A�W�A�̉���Ɠ��{�̈�Y�v�G�p���[�Q�T�U�`�V�y�[�W)
�W���[�W�E�r�E�J�i�w���i�A�����J�A�n���C���{�o�ϋ��c����ǒ��E�����w���m�j�̌��t
���{��̌R���C���h�l�V�A������`�̂��߂ɍs������X�̎d���̂Ȃ��ŁA�ł��d�v�Ȃ��̂̈�́A���K�R�y�R���g�D��n�݂��āA����ɌP����^�������Ƃł���B
�i�����j
�C���h�l�V�A�l���y�R���g�D��n�݂��āA����ɌP����^�������Ƃł���B
�C���h�l�V�A�l���R���P���������Ƃ̈Ӌ`�͋ɂ߂ďd�v�Ȃ��̂ł������B
���ꂪ��̃C���h�l�V�A�v���R�̑啔���̏��Z�Ɖ���̕��m�ƂȂ�A���A���Ă����I�����_���͂ƓƗ���키�ۂ̊�ՂƂȂ����B
���{�ɂ���ė^����ꂽ���̂悤�ȋ@��Ȃ������Ȃ�A���̃C���h�l�V�A�����v���̌o�߂͈�������̂ɂȂ��Ă����ł��낤�B
�i�㓡�����u���{�R���ƃC���h�l�V�A�Ɨ��v�P�o�ŎЁ@�P�W�U�y�[�W�j
�I�[�G���E���e�B���A�i�A�����J���ې����]�_�Ɓj�̌��t
�u�^��p�ȍ~�ŏ��̓�N�Ԃ̓��{�̏����́A
�A�W�A�̐��͂��͂���Â��W���������ʂ��A
��ɕ����Ȃ��Ȃ����A�W�A���c�����v
�u���{�����h�Ɂ@���Ƃ������Ƃ́A�A�W�A�ɂ�����A���n�鍑�̂P�X���I�I�\����j�����Ƃł���v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
(The Situation in Asia)
�h�S�[�����R�i��̃t�����X�哝�́j�̌��t
�V���K�|�[���̊ח��́A���l�A���n��`��
�������j�̏I������Ӗ�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�i�S����̃����h���ŃV���K�|�[���ח���m�������̓��L���j
�A�[�m���h�EJ�E�g�C���r�[�i�C�M���X�A���j�w�ҁj�̌��t
����ɂ����āA���{�l�����{�̂��߂Ƃ��������A�ނ���푈�ɂ���ė��v�����X�̂��߂ɁA�̑�Ȃ���j���c�����Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B
���̍��X�Ƃ́A���{�̌f�����Z���ȗ��z�ł������哌�����h���Ɋ܂܂�Ă������X�ł���B
���{�l�����j��Ɏc�����Ɛт̈Ӌ`�́A���m�l�ȊO�̐l�ނ̖ʑO�ɂ����āA�A�W�A�ƃA�t���J���x�z���Ă������m�l���A�ߋ���S�N�̊Ԃɍl�����Ă����悤�ȁA�s�s�̔��_�łȂ����Ƃ𖾂炩�Ɏ������_�ɂ���B�C�M���X�l���t�����X�l���A�����J�l���A�Ƃ����������݂͂ȏ����|���Ƀo�^�o�^�Ƃ���Ă��܂���
�i�P�X�T�U�N�i���a31�N�j�P�O���Q�W���A�p���u�I�u�U�[�o�[�v�j
�p���ŐV�ŗǂ̐�͓�ǂ����{��R�ɂ���Č������ꂽ���Ƃ́A
���ʂɃZ���Z�[�V���i�����܂��N�����o�����ł������B
����͂܂��i���I�ȏd�v�������o�����ł��������B
�Ȃ��Ȃ�P�W�S�O�N�̃A�w���푈�ȗ��A���A�W�A�ɂ�����p���̗͂́A���̒n��ɂ����鐼�m�S�̂̎x�z���ے����Ă�������ł���B
�P�X�S�P�N�A���{�͂��ׂĂ̔m�����ɑ��āA���m�͖��G�łȂ����Ƃ�����I�Ɏ������B
���̌[�����A�W�A�l�̎m�C�ɋy�ڂ����P�v�I�ȉe���́A�P�X�U�V�N�̃x�g�i���ɖ��炩�ł���B
�i���a�S�R�N�R���Q�Q���@�u�����V���v�j
H�EG�E�E�F���Y�i�C�M���X�@���j�w�ҁj�̌��t
���̑��͐A���n��`�ɏI�~����ł��A���l�ƗL�F�l��Ƃ̕����������炵�A���E�A�M�̊��������
���C�X�E�}�E���g�o�b�e���叫�i�C�M���X�R����A�W�A���i�ߕ��i�ߊ��j�̌��t
�u���ĕs�s���ւ������{�R���A���N�̎����ɁA�^�߂��C���{���{���ƂȂ�A
�@����������̂��s���̐��_�͂����������B
�@�w���̕���ƋQ��ɒǂ��߂�ꂽ�Ƃ��A�O�r�ɉ��������̂͐��n���������B
�@���{�R�̓C���p�[���ɂ����āA�܂��S�r���}�ɂ����Ĕs���ׂ����Ĕs�ꂽ�B
�@�����ł���B
�@�������A�����ɉ������c�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��z�L�u�r���}����̑�t�P�v
���A���́u�����v�ɂ��ă}�E���g�o�b�e���叫�͎��̂悤�Ɍ����Ă���B
�u����͎j�w�̌��Ѓg�C���r�[���A���݂��������j�����ʂ�ł���B
�@�����A�s���{�ɂ��āA�_���g���������������̂�������A
�@����͋����킪���̊�̐����l���A�A�W�A���̒n�ʂ���ǂ����Ƃ����Ƃɂ������̂��t
�u�@���{�R�̓A�A�W�A�������̊�O�ŁA
�@�ނ炪�ƂĂ����Ȃ�ʂƎv���Ă����@���ČR���@�ꋓ�ɔ��j�����B
�@�A�ƂĂ��Ɨ��̈ӎv���\�͂��Ȃ��Ǝv���Ă����A���n������
�@�펞���̒Z���Ԃ̑g�D���P�����A����Ȉ����S���������āA
�@�R���͂��s���͂����Ⴆ�����ɕϖe�������B
�@������smetamorphosis�i���p�I�ω��j�t�𐋂��������B
�@���̂��Ƃ́A�����̘A���R�̒N�����\�z�ł��Ȃ����Ƃł������B
�B���{�R�͔s�킷��ƁA�A���R�Ƃ̊ԂɌ��킳�ꂽ��틦��Ɋ�Â��āA
�@�@����͑S���A���R�Ɉ����n�����ƂɂȂ��Ă����B
�@�Ƃ��낪�A���{�R�̓C���h�l�V�A�R�Ɂs���킪�D��ꂽ�t�Ə̂���
�@�I���ɗ��ŕ����n���Ă����B
�@�@����ɂ���āA����܂Łs�L�t�̂悤�ɂ��ƂȂ��������C���h�l�V�A�l���s�Ձt�ɕϐg���A
�@�@���ɓƗ���B�������̂ł���B
�@�@�@�i���{�R�Ɋւ�����j
�܂��A�}�E���g�o�b�e���i�ߊ��ɂ��āA���̂悤�Șb������B
�C���h�Ɨ��̂��߂̍H�������������s�������C���p�[���ւ̈⍜���W�����̂��߃C���h���ƌ����A���a�T�O�N(�P�X�V�T�N�j�ɖ�����������������A���n�̐l�X�̗\�z�O�̋��͂ċA�������B
���̖͗l�Ɠ��{�䏊�ɎQ�サ�A�c���q�a���i����V�c�É��j�ɕ��ꂽ�Ƃ���
�c���q�a�����A�}�E���g�o�b�e�������̌��t�����ɂȂ�ꂽ�B
����͎��̂悤�Ȃ����t�ł���B
�u��������̕��f���āA���̎��悪�����������܂����B
�@�挎�A�l�p�[�������̑Պ����ɎQ���߁A�p�[�e�B�̐ȂŁA
�@�p����Ȑ����E�}�E���g�o�b�e�����������𑨂��āA���Ƃ������
�@�s�߂���푈���A���������A���R���i�ߊ��Ƃ��āA��ɐ��őΐ킵��
�@�@���{�R�����́A���̒����A�E���A�K���������ɂ����āA
�@�@�Í��������ނ̐����ł����B
�@�@���̂悤�ȑf���炵�������́A���ア����̍��ɂ����܂�邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�t
�ƌ��܂��Ă��ꂽ�v
�@�@�i������s�u�i�߃f���[�ցv�̔����ɑz���j
�_�O���X�E�}�b�J�[�T�[�i�A�����J�A���{��̘A���R�ō��i�ߊ��E�����j�̌��t
���{�̐��ݘJ���҂́A�ʂɂ����Ă����ɂ����Ă��A��������܂Œm���Ă���Ȃ��̂����Ƃ����h�Ȃ��̂̈�ł���B�������A�ނ�͘J���͂͂����Ă����Y�̊�b���ނ������Ȃ��B
���{�ɂ͎\�̂ق��Ɏ�藧�ĂĂ����ׂ����͉̂����Ȃ��̂��B
���{�l�́A�������ޗ��������f���ꂽ��i�o�ϕ������ꂽ��j�P�疜����P��Q�S�������Ƃ���̂ł͂Ȃ����Ƌ���Ă����B
����̂ɁA���{������E���ɕ������ړI�́A���̂قƂ�ǂ��A���S�ۏ�̂��߂ł������B
�i�P�X�T�P�N�T���R���A�ď�@�̌R���O�������ψ���̒�����ɂ����锭���j
���C�X�E�A�����i�C�M���X�A�_�[������w�����E�r���}�����w���Z�j�̌��t
�C�M���X�R�ɑ��Đ�����C���h�̗��蕔���i�`�����h���E�{�[�X�̗����鍑���R�iINA�̂��Ɓj�̓f���[�̐Ԃ��v�ǁi���b�h�E�t�H�[�g�j�ŁA�ނ�O�l�̏��Z�ɑ�\����ČR���ٔ��ɂ�����ꂽ�B���̍ٔ��̔����́A����ȑO�̎O�N�Ԃ̐킢�����A�C���h�Ɨ���������̂ɁA���傫�����ʂ��������B
�@�@�@�@�@�@�i�����r��E���������u���{�R���e�����������v���쏑�[�A�Q�W�SP�j
���X���b�v�E�X�^�b�_�[�h�i�A�����J�A���j�w�ҁj�̌��t
���łɎl�S�N�̊ԁA�A���I�����ɂ���āA���l�͖{�\�I�Ɏ��Ȃ̖c���͖����Ɍp��������̂ƐM����Ɏ������B
�P�X�O�S�N�̓��I�푈�ȑO�ɂ́A���Ȃ̖c������~����Ƃ����悤�Ȏv�z�͔��l��l���̈�l���l������Ȃ������B
�i�����j
�P�X�O�O�N�́A�l�S�N�Ԃ݂Ȃ��藈�������l�����̒��_�ł������B
���l�͂��̂Ƃ��A�Ж��Ǝ��͂̒���ɒB�����̂ł���B
���̌�킸���l�N�ɂ��ē��{�͖ґR�N�����ĘI���ɍR���A�����`�ɋ��C�e�𗁂т����E�����������B
���̙��߂ɔ��l�̑ޒ����n�܂����B
�i�����P���u�L�F�l��̖u���v�����ЁA�P�S�V�A�P�T�P�y�[�W�j
�j�~�b�c�����i�A�����J�@�����m�͑��i�ߒ����j
�u���̓���K���������̍��̗��l�B��B
�̋��ɋA������`���Ă����B
���̓�����邽�߂ɁA���{�R�l�͑S���ʍӂ��ĉʂĂ��B
���̑s��ɂ܂�E�C�Ƒc����z���S�����I�v
�@
�@
�@�X���������i�C�M���X��\�l�R�i�ߊ��j
�u��������A��߂��A���Ă����g��E�o������ړI�łȂ��{���̍U���̖ړI���ȂāA������җ�ȍU�����s�������{�̑�O�\�O�t�c�̔@���́A�j��ɂ��̗��w�nj��Ȃ��ł��낤�v�B
�i�u�s�k���珟���ցv�j
�u�@�����̔@���]�݂̂Ȃ��ړI��Nj�����R����̕��ʂ����ƍl���悤�Ƃ��A���̊�}���s�������{�R�l�̍ō��̗E�C�Ƒ�_�s�G���͋^���]�n���Ȃ��B���͔ޓ��ɔ䌨�����ׂ��@���Ȃ闤�R���m��Ȃ��B�v
�i����j
�@